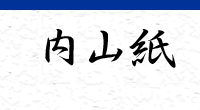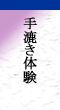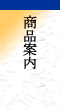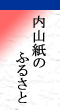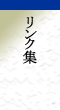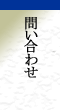内山紙について
内山紙の製造工程
このページでは伝統的な手すきの工程を紹介しています。製造工程自体に大きな差異はありませんが、写真の多くは昭和40年代に撮影したものを使用しているため、現在使用していない装置や手法の写真も掲載しています。(例:裁断は現在機械で行っているなど)
| 1 | 楮(コウゾ)の栽培 |
  コウゾはクワ科の植物で、人家に近い山地や田畑の脇に自生します。1年で約2メートルほどに育ち、樹皮の部分の繊維を和紙の原料として使用します。和紙の原料として使用するものは専用に栽培したもので、飯山に雪が降る前の11月中旬に刈り取ります。 コウゾはクワ科の植物で、人家に近い山地や田畑の脇に自生します。1年で約2メートルほどに育ち、樹皮の部分の繊維を和紙の原料として使用します。和紙の原料として使用するものは専用に栽培したもので、飯山に雪が降る前の11月中旬に刈り取ります。 |
|
| 2 | 蒸煮・皮はぎ・黒皮乾燥 |
  採取したコウゾは80センチから1メートルほどの長さに切って結束し、これを大釜で蒸します。熱く柔らかい内に原料となる皮の部分をはぎ取ります。 採取したコウゾは80センチから1メートルほどの長さに切って結束し、これを大釜で蒸します。熱く柔らかい内に原料となる皮の部分をはぎ取ります。  はいだ皮を黒皮と呼び、これを天日に干して乾燥させます。軒先に黒皮が干されている様は、かつては奥信濃の冬の風物詩でした。 はいだ皮を黒皮と呼び、これを天日に干して乾燥させます。軒先に黒皮が干されている様は、かつては奥信濃の冬の風物詩でした。 |
|
| 3 | 凍皮・皮かき |
 乾燥した黒皮を水に浸して十分に水を含ませてから、夜間屋外に放置して凍らせます。これを3回ほど繰り返すことで表皮をはぎ取りやすくするのです。凍結した黒皮の表皮を「おかき」と呼ばれる道具を使いかき落とします。 乾燥した黒皮を水に浸して十分に水を含ませてから、夜間屋外に放置して凍らせます。これを3回ほど繰り返すことで表皮をはぎ取りやすくするのです。凍結した黒皮の表皮を「おかき」と呼ばれる道具を使いかき落とします。  |
|
| 4 | 雪さらし |
  皮かきをした後の黒皮は、編み縄に編み付けて雪の上に広げ、まばらに雪をかけます。この状態で約1週間ほど天日にさらすと、雪が融ける際に発生するオゾンによってコウゾが漂白されます。新雪が降った翌日などには一家総出の作業で雪さらしが行われます。さらし終わった状態を白皮と呼び、白皮は天日で乾燥させます。 皮かきをした後の黒皮は、編み縄に編み付けて雪の上に広げ、まばらに雪をかけます。この状態で約1週間ほど天日にさらすと、雪が融ける際に発生するオゾンによってコウゾが漂白されます。新雪が降った翌日などには一家総出の作業で雪さらしが行われます。さらし終わった状態を白皮と呼び、白皮は天日で乾燥させます。 |
|
| 5 | 煮熟(しゃじゅく) |
  繊維を柔らかくするために白皮をアルカリ剤の入った釜で煮ます。アルカリ剤としては炭酸ソーダ・苛性ソーダの水溶液を用います。繊維を最も傷めにくいことから古くから藁灰が使われてきました。煮熟したあとは水でアルカリを洗い流します。 繊維を柔らかくするために白皮をアルカリ剤の入った釜で煮ます。アルカリ剤としては炭酸ソーダ・苛性ソーダの水溶液を用います。繊維を最も傷めにくいことから古くから藁灰が使われてきました。煮熟したあとは水でアルカリを洗い流します。 |
|
| 6 | 漂白・ふしひろい |
  昔は無かった工程ですが、和紙により一層の白さが求められるため、現在ではさらし粉や次亜塩素酸ソーダによる漂白を行います。漂白した繊維に混ざっている枯れ皮、節、ゴミを取り除いておきます。 昔は無かった工程ですが、和紙により一層の白さが求められるため、現在ではさらし粉や次亜塩素酸ソーダによる漂白を行います。漂白した繊維に混ざっている枯れ皮、節、ゴミを取り除いておきます。 |
|
| 7 | 打解(だかい) |
  打解機に白皮を入れ、苛性澱粉を加えながら1時間ほど叩き、繊維を一本一本に解きほぐします。 打解機に白皮を入れ、苛性澱粉を加えながら1時間ほど叩き、繊維を一本一本に解きほぐします。※1〜7までの複雑な工程が「原料調整作業」で、手漉きにかかる前処理です。 |
|
| 8 | 玉造り・小振り |
  打解したコウゾの皮は約1キログラムずつの玉状にまとめます。玉状にまとめるのは「漉き舟」と呼ばれる水槽に入れる原料を量るためです。漉き舟には水が約600リットル入り、これに対して玉4個を入れます。さらに水中の繊維を均一にするために黄蜀葵(おうしょっき:通称トロロアオイ)の根のしぼり汁(ニレ)を15リットル加えて攪拌します。この作業を「コブル」と呼びます。 打解したコウゾの皮は約1キログラムずつの玉状にまとめます。玉状にまとめるのは「漉き舟」と呼ばれる水槽に入れる原料を量るためです。漉き舟には水が約600リットル入り、これに対して玉4個を入れます。さらに水中の繊維を均一にするために黄蜀葵(おうしょっき:通称トロロアオイ)の根のしぼり汁(ニレ)を15リットル加えて攪拌します。この作業を「コブル」と呼びます。 |
|
| 9 | 漉き |
  溶解された白液の中から紙の繊維を簀桁(すけた)ですくい取ります。簀桁の端々までが均一の厚さになるように、簀桁を縦横に振りながら余分な水分を振り落とす作業を何回も繰り返します。これを流し漉きと呼びます。 溶解された白液の中から紙の繊維を簀桁(すけた)ですくい取ります。簀桁の端々までが均一の厚さになるように、簀桁を縦横に振りながら余分な水分を振り落とす作業を何回も繰り返します。これを流し漉きと呼びます。一枚の紙の中で均一な厚さを保つのはもちろん、さらにすべての紙が同じでなければならないのですから、微妙な感覚と経験が必要とされる作業です。「紙は気を漉く」といわれたほど精神状態が反映される作業なのです。したがって20年以上の経験を持つ年配者が漉いた紙が良い紙とされてきました。   昔から内山紙の製造は家族全員で行いました。雪の朝は一家総出でコウゾを雪にさらします。しかし流し漉きは男の仕事とされています。それは冬の寒い日に、手が切れそうな冷たい水の中で、手を休めることなく常に前後座右に簀桁を動かし続けなければならないきつい仕事だからです。作業の途中で一瞬でも手を休めると紙の生命は絶たれてしまうほどに繊細で厳しい仕事で、何十年も年季を積んだ親父が培った経験と勘が必須です。手漉きでは一日に200枚を漉くのがやっとなのです。 昔から内山紙の製造は家族全員で行いました。雪の朝は一家総出でコウゾを雪にさらします。しかし流し漉きは男の仕事とされています。それは冬の寒い日に、手が切れそうな冷たい水の中で、手を休めることなく常に前後座右に簀桁を動かし続けなければならないきつい仕事だからです。作業の途中で一瞬でも手を休めると紙の生命は絶たれてしまうほどに繊細で厳しい仕事で、何十年も年季を積んだ親父が培った経験と勘が必須です。手漉きでは一日に200枚を漉くのがやっとなのです。 |
|
| 10 | 圧搾・乾燥 |
  漉きあげた紙はまず圧搾機で圧力をかけて余分な水分を絞り出したあと、熱した鉄板に一枚ずつ敷いて乾燥させます。さらに不良品を選別して一帖(48枚)ずつにまとめておきます。 漉きあげた紙はまず圧搾機で圧力をかけて余分な水分を絞り出したあと、熱した鉄板に一枚ずつ敷いて乾燥させます。さらに不良品を選別して一帖(48枚)ずつにまとめておきます。
|
|
| 11 | 裁断・紙つぎ |
  裁断機を使って縦28.1センチ、横40.6センチの大きさに切りそろえます。障子紙の場合はさらに糊で48枚を横につなぎ合わせて19メートルの長さにする紙つぎを行い、一帖ごとに巻いた状態に包装して内山障子紙となります。筆墨紙の場合は裁断した状態の紙を二十五帖(1,200枚)単位で包装します。二十五帖のまとまりを一丸と呼びます。 裁断機を使って縦28.1センチ、横40.6センチの大きさに切りそろえます。障子紙の場合はさらに糊で48枚を横につなぎ合わせて19メートルの長さにする紙つぎを行い、一帖ごとに巻いた状態に包装して内山障子紙となります。筆墨紙の場合は裁断した状態の紙を二十五帖(1,200枚)単位で包装します。二十五帖のまとまりを一丸と呼びます。   |